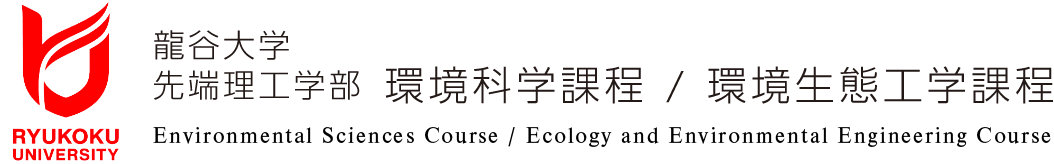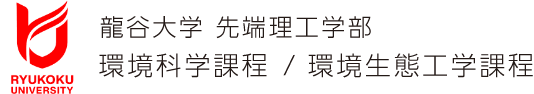三木教授が参画する国際共同研究グループが、生物多様性の重要度を世界各地で比較した論文を発表しました。日本からも多くの科学者が参加し、琵琶湖、霞ヶ浦、印旛沼と新川における長年の地道な観測に基づく貴重なデータが活用されました。三木教授はデータ解析の枠組み作りで貢献しました。
一次生産のような物質代謝は自然の恵みの土台であり生態系機能と呼ばれています。生態系機能が高く維持できるのは、環境が良いからでしょうか、それとも多様な生き物が互いに補い合ってがんばっているおかげでしょうか?
この研究では、生物が多様であること(= 生物多様性)の重要度に地域差があることを発見しました。どうやら、琵琶湖のように生物多様性が高く貧栄養な生態系ほど、生態系機能にとって生物多様性の重要度が大きくなる傾向があるようです。
つまり、生物多様性の高い地域を重点的に保全すれば、地球温暖化や富栄養化などの環境の悪化が自然の恵みに与えるマイナスの影響をある程度抑えることができることが分かりました。
詳しくは無料公開中の論文をダウンロード!